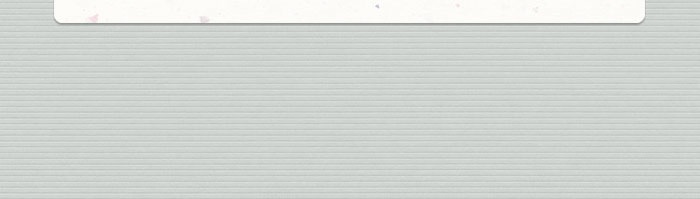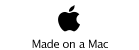事実

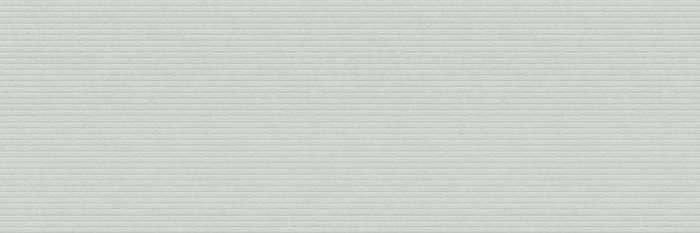
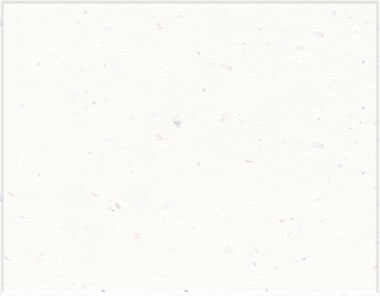

私たちは「事実」を知りたい、と願っていることがしばしばあります。「事実」とは何か、ということは難しい問題です。科学の世界では客観的なデータの蓄積とその解釈や解析によって「事実」を構築します。したがって、「事実」は実験、観察、観測、調査などによってのみ確かめることができ、長い時間をかけて判断されます。また、科学的手法は精度などの限界を本質的に持ちますから、そのために科学は歯切れが悪くなります。わからないことの方が多いくらいです。 否定は反例の発見により比較的できますが、肯定は難しい場合があります。 肯定したとしても「〜の可能性が高い。」「〜と考えられる。」といった具合です。一方で、本当かどうかわからなくても、心地よい二択は迷っている相手を納得させてしまいます。「〜が良い。」「〜が悪い。」「〜をだれもが使っている。」「〜しないとたいへんなことになる。」「〜は許されない。」「〜はすばらしい。」自分で考える力がなければ、誰かが言ったことにすぐに振り回されて、不安になってしまいます。
また、科学的な「事実」とはことなり、個人的にそうだ、ということもまた「事実」として存在することもまた「事実」です。妖怪の存在を科学的には証明できなくても、それを「事実」として信じることは別に問題ではありません。私も水木しげるさんが再発見した日本の妖怪の世界は大好きです。だれでもお守りの一つも持っています。トップアスリートがチタンのネックレスをつけています。おみくじを引き、星占いを気にします。ただ、それぞれが信じて良い(信じることで平常心が生まれて力が出るなど、効果も考えられる)ということがまた、うさんくさい「事実」に振り回される要因となることも注意しなくてはなりません。(おみくじを木に結びつけて厄をおとしてしまう、一年使ったお札を納めに行くなど、悪い結果に振り回されないしくみは、影響の緩和方法、かつ、お商売としておもしろいですね。)
断定的に商品を絶賛しながら、「使用者の感想です。」「個人の感想です。」と画面に小さくうつるCMを見るたびに、やれやれと思います。これは上で述べたことをうまく組み合わせて、消費者に商品を購入をすすめている一つの例だと思います。それをやっているのが有名な企業やTV局だしね。TVに出ている人はえらい、と思っている子どもはたくさんいるでしょうね。また、どれほどまじめに取材したニュースや番組でもそこには記者や取材者の主観が入っているはずです。私はこう考えました、というレポートであり、その人が実績や信用のある人であれば、信じる。署名のないニュースに価値を見いだすのは難しい。おかしなことをよく言っている人の書いたものに価値を見いだすことは難しい。この文章に価値があるかどうかも、わからない、といえます。
科学にできることは論理的に考える力を養う教育だと私は思っています。自分で考えて自分のことを処せるようになることが大事だと思います。
学者は仕事として表現する必要があります。「発表せよ、さもなければ立ち去れ」、私はこのことを十分に達成できていませんが、それをめざして事実を求めて研究しています。
2012年4月25日水曜日
事実